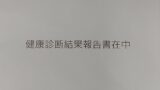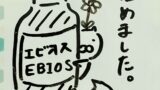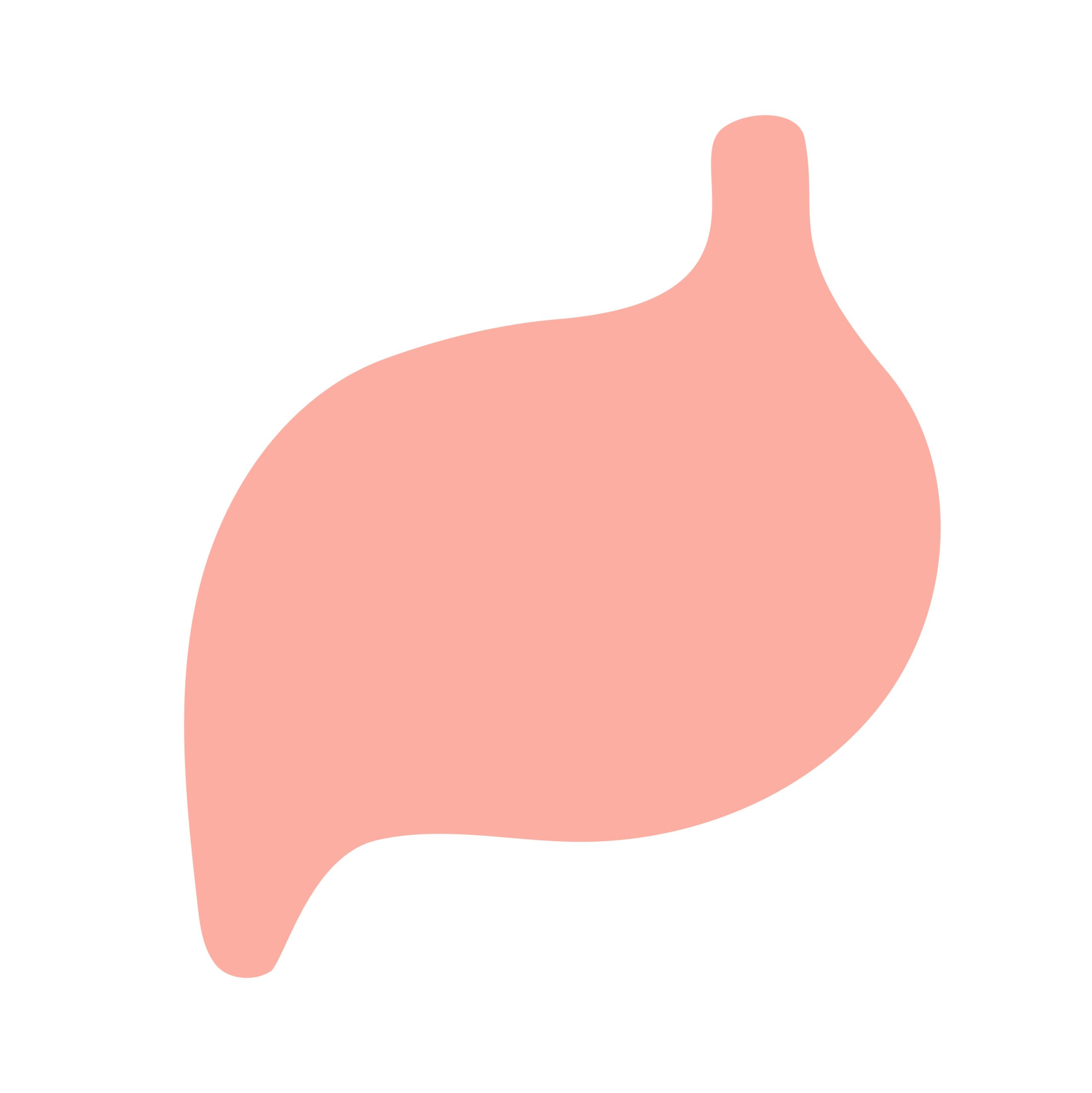私はここ3年ほど前から、毎日体重や体脂肪率を記録しています。
目的は健康維持の為です。
その記録を見返して、思ったことがあります。

最近チートデイ頻繁にやってるけど、太ってないな~。
ということです。
今年に入ってから、結構頻繁にチートデイを行っていますが、不思議と太っていません。
ちなみにチートデイの頻度は1週間に1~2回はやってます。
今回はチートデイを1週間に1~2回やってても太らない理由を考察したいと思います。
体重・体脂肪率の推移
直近1ヶ月半の体重と体脂肪率、体脂肪のグラフです。
私の体重は平均で63kg、体脂肪率は14%~16%を行ったり来たりです。
約1ヶ月半の間、ほぼ横ばいです。
縦の赤線がチートデイ日です。
思い返して見ると、チートデイの翌日から2、3日はカロリー制限していました。
太ってない理由はおそらくそれだと思われます。
チートデイから数日のカロリー
1日目:チートデイ
チートデイ当日の摂取カロリーはおおよそ3500~5000kcalです。
3000kcalはおよそ『すき家』のキング牛丼1杯分です。
私の1日の消費カロリーが約1800~1900kcal(基礎代謝含む)なので、チートデイによる過剰カロリーはおおよそ+1500~2500kcalになります。

チートデイにより一時的に代謝が上がっていると思うので、もしかしたら消費カロリーが上乗せされているかもしれません。
2日目:大きくカロリー制限
2日目はサラダチキンとかの食事内容が多かったです。
摂取カロリーは多分1日で800kcalぐらいだったかと思います。
1日の消費カロリーが1800~1900kcalなので、この日で差し引き-1100kcalぐらいです。
3日目以降:基礎代謝まで
3日目以降は基礎代謝分ぐらいのカロリー摂取でした。
なので、『1日1食+間食』なことが多かったです。

間食はプロテインなどですね。
私の基礎代謝が1500~1600kcalぐらいなので、1日あたりで差し引き-400kcal~-500kcalぐらいになります。
差し引きのカロリー量
チートデイ後の3日目~4日目でチートデイでの過剰カロリー(+1500~2500kcal)の精算が出来ていると思います。

多分、カロリー的に絶妙に釣り合いがとれているのでしょう。
前に紹介したチートデイ後のカロリー制限をハイペースでやってる感じですね。
身体への負担
巷で人気の16時間断食の『オートファジー効果』とかありますけど、

オートファジー?なにそれ??
的な感じで全く意識していません。
結果的にはそうなってしまっているだけで、あくまでもカロリー計算に沿ってやってます。
ストレスに関しては、2ヶ月もやってればこの生活スタイルに慣れて苦痛を感じなくなってきます。
最初からそれほど苦痛は感じてませんでしたが(;^_^A
でも、

『絶対体に悪いんだろうな~』
とは頭の片隅で思っています。
チートデイのお陰でインスリンがドバッドバ出ちゃってますから、身体への負担の方が心配です。
よく、

『オートファジー云々だから16時間の断食時間を作りなさい~』
とか推奨されていますけど、この生活スタイルなら普通にそれが出来てしまっています。

特に意識していませんが…。
急激な血糖値上昇の体の負担がオートファジー効果とかで相殺されてれば良いのですがね…(‘◇’)ゞ。
今のところは体に不調はないので問題はないと思います。

早く健康診断やりたいですね~。
快便
う〇こは腸活のお陰か毎日出てるし、チートデイの3日後ぐらいに爽快なぐらいめっちゃう〇こが出ます。

腸活のお陰でう〇こが皆勤賞になってます。
腸活やってるお陰で食べ物を効率良くエネルギーに変換して代謝が良くなっていると思いたいですね。
スポンサーリンク
感じたこと
この生活を続けてて感じたことは、

やっぱりカロリーは気にした方が良いな~
ということです。
チートデイしたら12時間ぐらいは身体にエネルギーが供給され続けてるでしょうし、グリコーゲンも枯渇するまでに2日ぐらいはかかります。
なので、

チートデイの翌日は最悪断食でも良いかも~。
なんて思ってたりもしました。
というか、1日絶食しただけでいちいち筋力低下してたら生きていけないでしょうし…笑
人間も動物なので、その辺の機能は狩猟生活から衰えはしてても遺伝的に残っているとは思います。
何日も渡っての運動不足やカロリー不足で、筋力って低下するようですしね。
そう思ってチートデイ翌日に本当に何も食べなかったら、お昼ぐらいに極限にお腹空きました。
とりあえず空腹を紛らわせるぐらいの間食はしておくことに…。
3日目以降は基礎代謝分ぐらいのカロリー摂取で良いと判断。
もちろん基礎代謝まで摂るのは筋力低下防止の為ですね。
3日目と同じ内容を何日続けるかは、初日のチートデイでどれぐらい食べたか?によると思います。
3500kcalクラスのチートデイなら4日目にはもう次のチートデイを始めています。
ただ、5000kcalクラスのチートデイなら4日目にもある程度のカロリー制限はしてる印象です。

この辺りは個人のカロリー摂取やカロリー消費により大きく左右されます。
ちなみに5000kcalクラスのチートデイでは、朝に大盛りの定食食べて、昼に大盛りのカレー、夜にキング牛丼からの締めにチョコモナカジャンボのイメージです。
あくまで私のチートデイの一例ですが、フードファイターのような大食いでもないので5000kcalクラスのチートデイが限界です。
5000kcalクラス超ならそれ以上にチートデイではない日を設けた方が良さそうです。
逆を言えば、チートデイではなくカロリー制限日を設ければ長期的には痩せる可能性大となります。
まぁ、加齢で代謝が落ちないように筋トレはしてますが、その前に食が細くなって将来的にはチートデイも存分に出来なくなりそうですね(;´Д`)

代謝が落ちるのが先か、食が細くなるのが先か…。
最後に
現在はそんなこんなで3日~4日に1回チートデイをしてます。
で、痩せもしてないけど太りもしてないです。
体型を維持したい人の参考になれば幸いです。
ではでは。